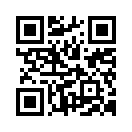2017年05月04日
悩んだ末に産業医を選択した理由
どうやら産業医の情報は人気があるようですので、産業医のことを投稿します。
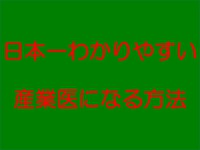
ピンコロ代表の忽那が、2年ぐらい専属産業医(常駐していてほぼ臨床からは離れる会社員生活)
および嘱託産業医(月に1回など定期的に会社に行くバイト的な産業医生活)をやってみた
経験から主観的な部分をまとめてみます。
産業医のメリット
1.健康な人を継続して把握できる
2.法律で決められているので病気の人がいなくなっても雇われる将来性(経験年数がモノを言うので早く始めるほど年収アップあり)
3.ホワイトな大企業でも大募集中(ワークライフバランス良し)
デメリット
1.企業的な価値観がないと心苦しい(金の切れ目が縁の切れ目)
2.実績が目に見えないことが多い(予防なので、数字で見えてくる)
3.メンタルヘルス扱う関係で恨まれ、訴訟のリスクがある
産業医資格を取る方法
2017年5月現在のところ、
産業医になるには大きく3つの方法*があります。
1:日本医師会の講習を受けてなる方法(更新制のため講習を受け続ける必要あり)。
2:福岡県にある産業医科大学に入学するという方法(更新不要)。
3:福岡県にある産業医科大学に短期入学(約1ヶ月)して講習を受けてなる方法(更新不要)。
現役でやっている産業医の先生の数で言うと1が一番多いですが、専属産業医という点でいくと、
おそらく2つ目が一番多くて、次が1つ目でしょうか。3つ目の私はレアキャラですね。
2007年の国の調査では産業医資格を持っている医師は約7万人だそうです。
*細かく言うと厚労省の出している4つの方法があります。
参考リンク(pdfです)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf
<収入に関しては…>
専属産業医としてやっても、嘱託産業医としてやっても一般的な臨床やっている医師と比べても遜色はありません。
大企業が求人を出しているのもあり、魅力的な福利厚生があったりするのも良いところです。
また残業などは基本的には発生しないので、時給換算したらかなり良い方だと思います。
収入に関しては細かくはご自身で検索してみてください。
有名な医師求人あっせんサイトで簡単に見つかります。
質問などありましたら、気軽にメッセージorコメントください。
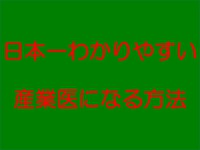
ピンコロ代表の忽那が、2年ぐらい専属産業医(常駐していてほぼ臨床からは離れる会社員生活)
および嘱託産業医(月に1回など定期的に会社に行くバイト的な産業医生活)をやってみた
経験から主観的な部分をまとめてみます。
産業医のメリット
1.健康な人を継続して把握できる
2.法律で決められているので病気の人がいなくなっても雇われる将来性(経験年数がモノを言うので早く始めるほど年収アップあり)
3.ホワイトな大企業でも大募集中(ワークライフバランス良し)
デメリット
1.企業的な価値観がないと心苦しい(金の切れ目が縁の切れ目)
2.実績が目に見えないことが多い(予防なので、数字で見えてくる)
3.メンタルヘルス扱う関係で恨まれ、訴訟のリスクがある
産業医資格を取る方法
2017年5月現在のところ、
産業医になるには大きく3つの方法*があります。
1:日本医師会の講習を受けてなる方法(更新制のため講習を受け続ける必要あり)。
2:福岡県にある産業医科大学に入学するという方法(更新不要)。
3:福岡県にある産業医科大学に短期入学(約1ヶ月)して講習を受けてなる方法(更新不要)。
現役でやっている産業医の先生の数で言うと1が一番多いですが、専属産業医という点でいくと、
おそらく2つ目が一番多くて、次が1つ目でしょうか。3つ目の私はレアキャラですね。
2007年の国の調査では産業医資格を持っている医師は約7万人だそうです。
*細かく言うと厚労省の出している4つの方法があります。
参考リンク(pdfです)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103897.pdf
<収入に関しては…>
専属産業医としてやっても、嘱託産業医としてやっても一般的な臨床やっている医師と比べても遜色はありません。
大企業が求人を出しているのもあり、魅力的な福利厚生があったりするのも良いところです。
また残業などは基本的には発生しないので、時給換算したらかなり良い方だと思います。
収入に関しては細かくはご自身で検索してみてください。
有名な医師求人あっせんサイトで簡単に見つかります。
質問などありましたら、気軽にメッセージorコメントください。
2016年12月25日
日本一わかりやすい産業医になる方法
突然ですが、筑波大学を卒業して、産業医をやりはじめた代表の忽那ですが、
医師の人にたまに尋ねられる、産業医になる方法について簡単にまとめておきます。
過去の記事では産業医の勉強会のまとめをしていきますとの記事がありましたが
(^◇^;)
*参考*産業医基礎前期研修会のまとめ(20120602更新)
http://health.tsukuba.ch/e166294.html
研修医生活が忙しく頓挫しておりました。。。
が、ひょんなことから2015年から(専属)産業医をしておりますので、
改めてまとめてみようかと思います。
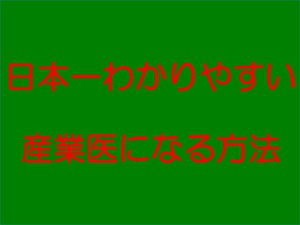
2016年12月現在のところ、
産業医になるには大きく3つの方法があります。
1:日本医師会の講習を受けてなる方法(更新制のため講習を受け続ける必要あり)。
2:福岡県にある産業医科大学に入学するという方法(更新不要)。
3:福岡県にある産業医科大学に短期入学(約1ヶ月)して講習を受けてなる方法(更新不要)。
現役でやっている産業医の先生の数で言うと1が一番多いですが、専属産業医という点でいくと、
おそらく2つ目が一番多くて、次が1つ目でしょうか。3つ目の私はレアキャラですね。
以上。が、産業医になる方法でした。
これ以上は誰かが注目してくれて、コメントなりアクセスが多くなってたらまた書きます笑
気軽にコメントくださいまし。
代表 忽那
医師の人にたまに尋ねられる、産業医になる方法について簡単にまとめておきます。
過去の記事では産業医の勉強会のまとめをしていきますとの記事がありましたが
(^◇^;)
*参考*産業医基礎前期研修会のまとめ(20120602更新)
http://health.tsukuba.ch/e166294.html
研修医生活が忙しく頓挫しておりました。。。
が、ひょんなことから2015年から(専属)産業医をしておりますので、
改めてまとめてみようかと思います。
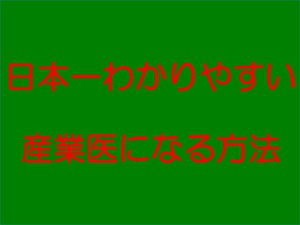
2016年12月現在のところ、
産業医になるには大きく3つの方法があります。
1:日本医師会の講習を受けてなる方法(更新制のため講習を受け続ける必要あり)。
2:福岡県にある産業医科大学に入学するという方法(更新不要)。
3:福岡県にある産業医科大学に短期入学(約1ヶ月)して講習を受けてなる方法(更新不要)。
現役でやっている産業医の先生の数で言うと1が一番多いですが、専属産業医という点でいくと、
おそらく2つ目が一番多くて、次が1つ目でしょうか。3つ目の私はレアキャラですね。
以上。が、産業医になる方法でした。
これ以上は誰かが注目してくれて、コメントなりアクセスが多くなってたらまた書きます笑
気軽にコメントくださいまし。
代表 忽那
2012年06月02日
産業医研修、全まとめ!その0
報告遅くなりました。
研修医生活はなかなか大変ですね。
2012年5月19~20日に行われた
「産業医基礎前期研修会」を振り返っていくシリーズです。
全部で14コマ講義があったので、その14まで!!
1コマずつ丁寧に、かつ、簡潔に振り返っていきたいと思います。
こんなブログ全国初!?かな??
では、振り返りまする。
の、前に、「産業医基礎前期研修会」ってなんだ?っていうところから。
産業医になるためには、大きく2つの方法があります。
1つは産業医科大学という、産業医の育成を主目的に作られた大学へ行く方法。
もう1つは私みたいに、普通の国立大学を卒業し医師免許を取得したあと、
産業医の研修を受けて取得するという方法。
そして、今回シリーズでお伝えしようとしているのは、
後者の産業医の大学に行ってない人が産業医になるために受ける必要のある研修の一部である、
「産業医基礎前期研修会」で学んだことであります。
免許取得まで50単位の研修が必要で、
この記事を書いている研修医の私は、14/50を修めたってわけでして、
これから実地研修などをやらなければいけないわけなんですね。
(T▽T)
ということで、医師としてのキャリアも積みながら、
合間みて研修するのであと4年ぐらいはかかるのかな~って感じですね。
しかも、一度取得しても、免許更新制なんでまた講習も受けなければいけないという。
生涯勉強です。
~~~~~~~~~~
リアルに詳しく知りたい人は、
茨城県が公開している産業医認定制度に関するページを調べてみてください。
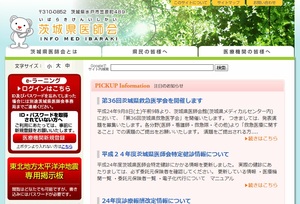
http://www.ibaraki.med.or.jp/?act=Doctor_authorization
(東京都医師会の方がわかりやすい・・・)
~~~~~~~~~~
ということで、産業医制度について長くなってしまったので、
次回から実際の講義を振り返っていきますので、お楽しみに!!
質問やツッコミなどありましたら、気軽に連絡くださいませ。
では(≧∇≦)/
研修医生活はなかなか大変ですね。
2012年5月19~20日に行われた
「産業医基礎前期研修会」を振り返っていくシリーズです。
全部で14コマ講義があったので、その14まで!!
1コマずつ丁寧に、かつ、簡潔に振り返っていきたいと思います。
こんなブログ全国初!?かな??
では、振り返りまする。
の、前に、「産業医基礎前期研修会」ってなんだ?っていうところから。
産業医になるためには、大きく2つの方法があります。
1つは産業医科大学という、産業医の育成を主目的に作られた大学へ行く方法。
もう1つは私みたいに、普通の国立大学を卒業し医師免許を取得したあと、
産業医の研修を受けて取得するという方法。
そして、今回シリーズでお伝えしようとしているのは、
後者の産業医の大学に行ってない人が産業医になるために受ける必要のある研修の一部である、
「産業医基礎前期研修会」で学んだことであります。
免許取得まで50単位の研修が必要で、
この記事を書いている研修医の私は、14/50を修めたってわけでして、
これから実地研修などをやらなければいけないわけなんですね。
(T▽T)
ということで、医師としてのキャリアも積みながら、
合間みて研修するのであと4年ぐらいはかかるのかな~って感じですね。
しかも、一度取得しても、免許更新制なんでまた講習も受けなければいけないという。
生涯勉強です。
~~~~~~~~~~
リアルに詳しく知りたい人は、
茨城県が公開している産業医認定制度に関するページを調べてみてください。
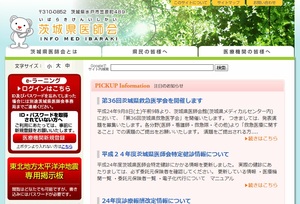
http://www.ibaraki.med.or.jp/?act=Doctor_authorization
(東京都医師会の方がわかりやすい・・・)
~~~~~~~~~~
ということで、産業医制度について長くなってしまったので、
次回から実際の講義を振り返っていきますので、お楽しみに!!
質問やツッコミなどありましたら、気軽に連絡くださいませ。
では(≧∇≦)/