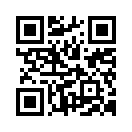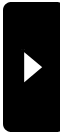2012年07月02日
熱中症、なりやすいのは?
みなさんこんにちは。
私の勤める中学校では、夏の総体(3年生にとっては最後となるかもしれない部活の大会)県大会に向けて、土日もガンガン練習しているところです。
そんなときに心配なのが、「熱中症」です。
昨年は、節電対策のために冷房を控えたことで、うまく体温調節ができずに病院に搬送され、熱中症と診断を受けた人が全国的に例年の倍以上でした。
さて、その熱中症ですが、なりやすい「タイプ」があると聞きました。ここでは学校生活に置き換えてご紹介したいと思います。
学校生活の中でリスクの高いものは”部活動”です。季節柄、どこの学校でも盛んに活動しています。その中で熱中症になりやすいスポーツが、ユニフォームが体に密着するタイプのスポーツ、だそうです。
例えば、剣道、柔道、野球など…
昨年の搬送例でも分かるように、屋内でも熱中症にかかります。学校生活でも同じく、屋内の部活動も注意が必要なのです。
また、体型においても熱中症になりやすいタイプがあるようです。
肥満・肥満傾向の人はハイリスクとのことです。体内の熱をうまく放散できなくなることが原因の一つと言われています。
いよいよ夏本番となるこれからの時期、体のラインも気になる季節。様々な場面で「適切な体重管理を。」と叫ばれているので、ぽっちゃり体型の私も何となくイヤな気持ちになりますが、熱中症予防でもそのようなことを言うことになり、さらに心苦しい限りです。でもやはり、どこかの誰かの健康管理に役立てば…と思い、綴りました。
ちなみに、最近「モヒートティー」を飲みました。さわやかな香りが夏にぴったりだと感じました。
水分補給にもオススメです。
みなさんも、自分のお気に入りドリンクを探しながら、熱中症対策をしてみてはいかがでしょうか♪
私の勤める中学校では、夏の総体(3年生にとっては最後となるかもしれない部活の大会)県大会に向けて、土日もガンガン練習しているところです。
そんなときに心配なのが、「熱中症」です。
昨年は、節電対策のために冷房を控えたことで、うまく体温調節ができずに病院に搬送され、熱中症と診断を受けた人が全国的に例年の倍以上でした。
さて、その熱中症ですが、なりやすい「タイプ」があると聞きました。ここでは学校生活に置き換えてご紹介したいと思います。
学校生活の中でリスクの高いものは”部活動”です。季節柄、どこの学校でも盛んに活動しています。その中で熱中症になりやすいスポーツが、ユニフォームが体に密着するタイプのスポーツ、だそうです。
例えば、剣道、柔道、野球など…
昨年の搬送例でも分かるように、屋内でも熱中症にかかります。学校生活でも同じく、屋内の部活動も注意が必要なのです。
また、体型においても熱中症になりやすいタイプがあるようです。
肥満・肥満傾向の人はハイリスクとのことです。体内の熱をうまく放散できなくなることが原因の一つと言われています。
いよいよ夏本番となるこれからの時期、体のラインも気になる季節。様々な場面で「適切な体重管理を。」と叫ばれているので、ぽっちゃり体型の私も何となくイヤな気持ちになりますが、熱中症予防でもそのようなことを言うことになり、さらに心苦しい限りです。でもやはり、どこかの誰かの健康管理に役立てば…と思い、綴りました。
ちなみに、最近「モヒートティー」を飲みました。さわやかな香りが夏にぴったりだと感じました。
水分補給にもオススメです。
みなさんも、自分のお気に入りドリンクを探しながら、熱中症対策をしてみてはいかがでしょうか♪
2012年06月25日
水泳学習(プール)が始まります!
7月を前にしたこの時期、各学校ではプール開きをする頃だと思います。
つくば市で実施されたプールの放射線量測定によると、市内小中学校、高校において放射性ヨウ素・放射性セシウムは共に不検出だったとのことで安心しているところです。
さて、プールが始まる時期に注意が必要な病気があります。それは、
「プール熱(正式名:咽頭結膜熱)」です。
症状としては、
①38~40度の高い熱が出る
②目(結膜)が真っ赤になる
③のど(咽頭)が痛くなる
などがあります。
学校で水泳授業が始まる頃に発生しやすく、プールで使ったタオルの貸し借りなどが原因で感染する、ということから「プール熱」という名前が付いたと言われています。
予防策としては、プールに入った後は、
”ていねいなうがい・手洗い”をすることと”清潔なタオルを使い(他の人と貸し借りしない)”、感染源を体内に入れないことです。
主に小学生を中心に流行する傾向があるそうです。
楽しいプール学習にするために、『環境と心身の両面から健康を守れるようにしていきたい。』と、改めて感じるこの頃です。
プール熱に限らず、みなさん、自分の健康を大切にしてくださいね♪
つくば市で実施されたプールの放射線量測定によると、市内小中学校、高校において放射性ヨウ素・放射性セシウムは共に不検出だったとのことで安心しているところです。
さて、プールが始まる時期に注意が必要な病気があります。それは、
「プール熱(正式名:咽頭結膜熱)」です。
症状としては、
①38~40度の高い熱が出る
②目(結膜)が真っ赤になる
③のど(咽頭)が痛くなる
などがあります。
学校で水泳授業が始まる頃に発生しやすく、プールで使ったタオルの貸し借りなどが原因で感染する、ということから「プール熱」という名前が付いたと言われています。
予防策としては、プールに入った後は、
”ていねいなうがい・手洗い”をすることと”清潔なタオルを使い(他の人と貸し借りしない)”、感染源を体内に入れないことです。
主に小学生を中心に流行する傾向があるそうです。
楽しいプール学習にするために、『環境と心身の両面から健康を守れるようにしていきたい。』と、改めて感じるこの頃です。
プール熱に限らず、みなさん、自分の健康を大切にしてくださいね♪
2012年06月18日
救急救命!
本日、本校において養護教諭主導で救急救命法についての校内研修(職員間での研修)を行いました。
2010年10月に心肺蘇生のガイドラインが「ガイドライン2010」に改訂されたことを受け、日本でも今年の4月1日から新方式が完全実施となったことから、変更点について学校職員が共通理解しよう、という趣旨で実施することになりました。
本校では、救急救命法について毎年1回は必ず職員研修しているのですが(他市町村では認定講習を義務付けているところもあるそう)、例年消防署の職員の方を講師に招いて講習をしいたのですが、今回は様々な理由から自前の研修になり、私自身はかなりプレッシャーのかかった日々でした…。
とにもかくにも学校内で専門的立場にいるのは養護教諭ですし、こんなときに存在感を示さないでいつ示す、勉強だ、と思って前向きに取り組み始めました。こんな義務感から始めた研修準備ですが、『どうしたら限られた時間の中で、正確に、分かりやすく伝えられるだろう。』と思いながらやっていると、何か楽しくなってきて、無事に終わった今、少し物足りなさすら感じているところです 笑。
また、今回は職員向けの研修でしたが、『子ども達にも保健指導としてできたら、これから生きていく上で何かのたしになるのではないか。』とも思いました。(学校のカリキュラム上、そうすぐには時間がとれないのですが…)
水泳学習も始まる時期ですし、このタイミングで職員研修ができたことはよかったです。
あとは、逆説的ですが、この研修が現実と結びつかないことを祈るばかりです。(もちろん心肺蘇生が必要な事態になったときは効果が発揮されることを祈ります。)
最後に、蛇足ですが今回のガイドライン改訂の主な項目を私なりにまとめてみました。参考までにご覧ください。
【ガイドライン2010 改訂点】
改訂① 人工呼吸→胸骨圧迫の順番から、胸骨圧迫→人口呼吸の順番へ変更された。
(血液循環に関して、胸骨圧迫の方の有効性が実証されたため)
改訂② 心停止の確認について、これまでは呼吸と脈拍の触知を同時に行うとされていたが、熟練者以外は 呼吸の有無の確認に専念するように、と変更された。
(脈拍の触知は困難を極めるため)
改訂③ AEDの成人用パッドの適応年齢が、8歳以上であったものが、6~7歳以上へと拡大された。
(現場の状況に合わせるため。小児用パッドの普及率が低かったためか?)
なお、変更点は上の3項目だけではありません。あくまでも、私が柱として大切だと感じたもののみ載せただけですので、その点はご了承ください。
人助けの第1歩として「知識を蓄える」、ということから始めてみるのもいいですよね♪
2010年10月に心肺蘇生のガイドラインが「ガイドライン2010」に改訂されたことを受け、日本でも今年の4月1日から新方式が完全実施となったことから、変更点について学校職員が共通理解しよう、という趣旨で実施することになりました。
本校では、救急救命法について毎年1回は必ず職員研修しているのですが(他市町村では認定講習を義務付けているところもあるそう)、例年消防署の職員の方を講師に招いて講習をしいたのですが、今回は様々な理由から自前の研修になり、私自身はかなりプレッシャーのかかった日々でした…。
とにもかくにも学校内で専門的立場にいるのは養護教諭ですし、こんなときに存在感を示さないでいつ示す、勉強だ、と思って前向きに取り組み始めました。こんな義務感から始めた研修準備ですが、『どうしたら限られた時間の中で、正確に、分かりやすく伝えられるだろう。』と思いながらやっていると、何か楽しくなってきて、無事に終わった今、少し物足りなさすら感じているところです 笑。
また、今回は職員向けの研修でしたが、『子ども達にも保健指導としてできたら、これから生きていく上で何かのたしになるのではないか。』とも思いました。(学校のカリキュラム上、そうすぐには時間がとれないのですが…)
水泳学習も始まる時期ですし、このタイミングで職員研修ができたことはよかったです。
あとは、逆説的ですが、この研修が現実と結びつかないことを祈るばかりです。(もちろん心肺蘇生が必要な事態になったときは効果が発揮されることを祈ります。)
最後に、蛇足ですが今回のガイドライン改訂の主な項目を私なりにまとめてみました。参考までにご覧ください。
【ガイドライン2010 改訂点】
改訂① 人工呼吸→胸骨圧迫の順番から、胸骨圧迫→人口呼吸の順番へ変更された。
(血液循環に関して、胸骨圧迫の方の有効性が実証されたため)
改訂② 心停止の確認について、これまでは呼吸と脈拍の触知を同時に行うとされていたが、熟練者以外は 呼吸の有無の確認に専念するように、と変更された。
(脈拍の触知は困難を極めるため)
改訂③ AEDの成人用パッドの適応年齢が、8歳以上であったものが、6~7歳以上へと拡大された。
(現場の状況に合わせるため。小児用パッドの普及率が低かったためか?)
なお、変更点は上の3項目だけではありません。あくまでも、私が柱として大切だと感じたもののみ載せただけですので、その点はご了承ください。
人助けの第1歩として「知識を蓄える」、ということから始めてみるのもいいですよね♪
2012年05月30日
ポリオワクチン
健康に過ごすために、予防接種はすごく大切ですよね。
インフルエンザなどの毎年流行の変わるウイルスは、毎年予防接種が必要です。
それと乳児が受けなければいけない予防接種もたくさんあります。
まだ免疫が確立していないので、予防してあげないと重篤な病態になってしまうんですね。
予防接種については、推奨されるスケジュールが出ていますので、参考にしてぜひ受けさせてあげてくださいね。
感染症情報センター
http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule.html
そこで最近話題のポリオワクチンについてです。
ポリオワクチンは、2012年9月から、不活化ワクチンが導入されます。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/oshirase.html
そもそもポリオとは、ポリオウイルスが起こす小児マヒのことを指すことが一般的です。
この病気は、WHOが根絶を目指していて、日本が含まれる西大西洋地域では、2000年に根絶宣言がされました。
つまり日本にはもうポリオはないんですね。
ただし、世界にはまだポリオが流行っている地域があるため、このグローバルな世の中、予防接種をすることが大切になります。
そして問題になっているのが、今までポリオが「生ワクチン」であったことです。
、弱毒化されたウイルスを予防のために接種していたために、非常に低い割合ながら、ワクチンを打ってしまったことでポリオにかかる子が出ていた、ということです。
ポリオを防ぐための処置でポリオになってしまう、これはとてもつらいことですよね。
でもそもそもなぜ生ワクチンが導入されたんでしょうか。
これは、1960、61年にポリオが大流行した際に、たとえ生ワクチンを接種してポリオになってしまう確率があるとしても、打たないより防げる!と声を上げたお母さんたちに答え、政府が緊急輸入したことが始まりです。
このときの母たちの想いと政府の決断には、すごく考えさせられますね。
「病気になった」ことは結果でわかりますが、「病気にならなかった」ことが予防の効果なのかどうかというのはとても分かりづらいものです。
それでも、予防できる感染症を予防することはとても大切なことです!
予防接種は受けるようにしましょう。
インフルエンザなどの毎年流行の変わるウイルスは、毎年予防接種が必要です。
それと乳児が受けなければいけない予防接種もたくさんあります。
まだ免疫が確立していないので、予防してあげないと重篤な病態になってしまうんですね。
予防接種については、推奨されるスケジュールが出ていますので、参考にしてぜひ受けさせてあげてくださいね。
感染症情報センター
http://idsc.nih.go.jp/vaccine/dschedule.html
そこで最近話題のポリオワクチンについてです。
ポリオワクチンは、2012年9月から、不活化ワクチンが導入されます。
厚生労働省
http://www.mhlw.go.jp/bunya/kenkou/polio/oshirase.html
そもそもポリオとは、ポリオウイルスが起こす小児マヒのことを指すことが一般的です。
この病気は、WHOが根絶を目指していて、日本が含まれる西大西洋地域では、2000年に根絶宣言がされました。
つまり日本にはもうポリオはないんですね。
ただし、世界にはまだポリオが流行っている地域があるため、このグローバルな世の中、予防接種をすることが大切になります。
そして問題になっているのが、今までポリオが「生ワクチン」であったことです。
、弱毒化されたウイルスを予防のために接種していたために、非常に低い割合ながら、ワクチンを打ってしまったことでポリオにかかる子が出ていた、ということです。
ポリオを防ぐための処置でポリオになってしまう、これはとてもつらいことですよね。
でもそもそもなぜ生ワクチンが導入されたんでしょうか。
これは、1960、61年にポリオが大流行した際に、たとえ生ワクチンを接種してポリオになってしまう確率があるとしても、打たないより防げる!と声を上げたお母さんたちに答え、政府が緊急輸入したことが始まりです。
このときの母たちの想いと政府の決断には、すごく考えさせられますね。
「病気になった」ことは結果でわかりますが、「病気にならなかった」ことが予防の効果なのかどうかというのはとても分かりづらいものです。
それでも、予防できる感染症を予防することはとても大切なことです!
予防接種は受けるようにしましょう。
2012年05月29日
今日は中間テスト!
私の勤める中学校は今日が前期の中間テスト。
1年生は初めてのテストということで、緊張の面持ち。
このような日、保健室は「開店休業」状態です。生徒が全く来ません。(休み時間の悪ふざけが理由のケガ人も、もちろんいません。)
”いつも休み時間になる度に来ていたあの子”も、”イヤな授業の前は必ず保健室に寄っていたあの子”も、”教室は何となく居心地が悪い…と言っていたあの子”も、目の前のテストに励んでいるのでしょう。
『なんだ、やっぱり気持ちの問題なんじゃん!(怒)』
と、思う自分がいます。でもそれと同時に、
『こんなふうにいつかの大事なときのために、子どもたちはエネルギーを貯めていたんだな、その一躍を保健室が担っているなら、それはそれでまぁ、いっか。』
と思う自分もいます。
忙しかったら忙しかったで不平をいい、暇なら暇で不平を言う。歳を重ねるごとに心がよごれてきた気がする私。
それに引きかえ、子どもって、すばらしいですね。
1年生は初めてのテストということで、緊張の面持ち。
このような日、保健室は「開店休業」状態です。生徒が全く来ません。(休み時間の悪ふざけが理由のケガ人も、もちろんいません。)
”いつも休み時間になる度に来ていたあの子”も、”イヤな授業の前は必ず保健室に寄っていたあの子”も、”教室は何となく居心地が悪い…と言っていたあの子”も、目の前のテストに励んでいるのでしょう。
『なんだ、やっぱり気持ちの問題なんじゃん!(怒)』
と、思う自分がいます。でもそれと同時に、
『こんなふうにいつかの大事なときのために、子どもたちはエネルギーを貯めていたんだな、その一躍を保健室が担っているなら、それはそれでまぁ、いっか。』
と思う自分もいます。
忙しかったら忙しかったで不平をいい、暇なら暇で不平を言う。歳を重ねるごとに心がよごれてきた気がする私。
それに引きかえ、子どもって、すばらしいですね。
2012年05月23日
人間関係に悩みが出てくる時期…
「この人(子)、ちょっと独特な性格もってるな。」と、感じることはありませんか?
性格が単に独特な場合が多いですが、発達障害があるかもしれない、という視点があると対応しやすくなることがあります。
時間にこだわる、先の予定が急に変わると理解できずイライラする、冗談が通じない…などが代表的なチェックポイントですが、もしそんな場面に出くわしたら、一つ一つ丁寧に相手に説明し、確認しましょう。
ぶっきらぼうだったり暴力的な言動の裏には、その人自身も「自分のことが自分でも相手にも理解されない」と悩んでいることがあります。
でも、程度の差こそあれ、誰でも一緒ですよね。保健室では日常茶飯事です。
それでは今日も1日楽しく過ごしましょう!
性格が単に独特な場合が多いですが、発達障害があるかもしれない、という視点があると対応しやすくなることがあります。
時間にこだわる、先の予定が急に変わると理解できずイライラする、冗談が通じない…などが代表的なチェックポイントですが、もしそんな場面に出くわしたら、一つ一つ丁寧に相手に説明し、確認しましょう。
ぶっきらぼうだったり暴力的な言動の裏には、その人自身も「自分のことが自分でも相手にも理解されない」と悩んでいることがあります。
でも、程度の差こそあれ、誰でも一緒ですよね。保健室では日常茶飯事です。
それでは今日も1日楽しく過ごしましょう!
2012年04月16日
今日の学校給食メニュー
みなさん、こんにちは。
とある中学校の保健室勤務をしています、『茨城健康学習塾 ピンピンコロリ』ブログの学校保健担当です。
本校の校庭の桜も葉桜になりつつあり、はかなさにも趣を覚える今日この頃。
今日の給食メニューをのぞくと…、
・スパゲティーミートソース
・チキンナゲット(小1~小4:2個、小5~中3:3個)
・パプリカサラダ(イタリアンドレッシング)
・バターロール
・牛乳
となっています。
洋食ですね♪
麺料理はなかなかお出ましにならないので、珍しい!
ご飯を出す日数を多めに設定しているからです(平均3.5回/週)。
学校保健的に見ると、今日のメニューで食物アレルギーの子はいなそう
(*^_^*)
みんな、残さず食べてね~
そしてみなさんも、今日のランチ、夕食、おいしくどうぞ。
自分の体をつくるのはその一口です。
とある中学校の保健室勤務をしています、『茨城健康学習塾 ピンピンコロリ』ブログの学校保健担当です。
本校の校庭の桜も葉桜になりつつあり、はかなさにも趣を覚える今日この頃。
今日の給食メニューをのぞくと…、
・スパゲティーミートソース
・チキンナゲット(小1~小4:2個、小5~中3:3個)
・パプリカサラダ(イタリアンドレッシング)
・バターロール
・牛乳
となっています。
洋食ですね♪
麺料理はなかなかお出ましにならないので、珍しい!
ご飯を出す日数を多めに設定しているからです(平均3.5回/週)。
学校保健的に見ると、今日のメニューで食物アレルギーの子はいなそう
(*^_^*)
みんな、残さず食べてね~
そしてみなさんも、今日のランチ、夕食、おいしくどうぞ。
自分の体をつくるのはその一口です。