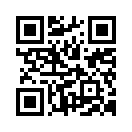2012年06月06日
なんで伝わらないのっ!
みなさん、こんにちは。
とある学校の保健室で勤務している私から、今日のタイトルにあるように、『なんで伝わらないかなぁ~』と思わせる人に、どう対応すればよいか、少しのヒントになればと思い、つづります。
平成14年の文科省の調査により、小学校において何かしらの配慮を要する児童の割合が6.3%だという結果が出ました。1クラス30人だと仮定すると、そのクラスに2人くらいはいる計算になります。
”何かしらの配慮を要する”とは、身体的介助が必要だとか、識字に支援が必要だということの他に、集中力がもたないことに対して工夫が必要であるとか、周りに合わせた行動ができるように支援が必要だということも対象になっています。
つまり、特別支援学校(一昔前には養護学校と言われていた学校)での教育は必要ではないが、
学校生活を送る上で周りと差が出る、又は、その子自身に不利益が出ると考えられる子どもの割合が示されたわけです。
さて、だからと言って治療をして治す、というものではありません。周りにいる人たちがその人の特性を理解し行動さえすればいいのです。(もちろん本人の自覚も必要ですが…)
大人になってもそういった特性は消えるのもではないので、
学校だけではなく、大人社会でも何かの参考になれば幸いです。
ヒント①:具体的な時間を示す
→落ち着きがなくなってきた人がいるとします。「もう少しだから我慢して。」ではなく、「あと10分で終わるから、それまで我慢して。」と伝えると、見通しがつきやすく、途切れがちな集中力がもつことがあるそうです。自分が考える”もう少し”と相手が考える”もう少し”は同じでない場合があります。
ヒント②:具体的な「もの」を示す
→ある物を移動してほしいとき。「これ、あっちに持ってって。」では伝わりにくいようです。そんなときは「この箱、隣の部屋に持ってって。」と言いましょう。指し言葉(これ・それ・あれなど)が何を示しているのか想像するのが苦手な特性があるので、抽象的な表現は避け、具体的な表現に変えるとよいようです。
ヒント③:環境を変える
→『もうそろそろ帰ってほしいのに、全くこちらの気持ちを察せてないなぁ。』と思うときはありませんか?相手の気持ちを推し量る、ということが苦手な人もいますので、そんなときは窓のカーテンを閉めたりして帰る準備を始めるなどの環境を変えると、『あ、帰る時間なんだな。』と相手も理解できるようです。
以上、色々と書きましたが、個性が一人一人違うように、同じ”困った”に対しても、対応は一人一人違うのが一般的なようです。上記のことは、私の経験から得たことも多いので、みなさんの中で応用していただければと思います。
長々と、おつきあいありがとうございました。対応についてはこれからも試行錯誤で頑張りたいと思います。
とある学校の保健室で勤務している私から、今日のタイトルにあるように、『なんで伝わらないかなぁ~』と思わせる人に、どう対応すればよいか、少しのヒントになればと思い、つづります。
平成14年の文科省の調査により、小学校において何かしらの配慮を要する児童の割合が6.3%だという結果が出ました。1クラス30人だと仮定すると、そのクラスに2人くらいはいる計算になります。
”何かしらの配慮を要する”とは、身体的介助が必要だとか、識字に支援が必要だということの他に、集中力がもたないことに対して工夫が必要であるとか、周りに合わせた行動ができるように支援が必要だということも対象になっています。
つまり、特別支援学校(一昔前には養護学校と言われていた学校)での教育は必要ではないが、
学校生活を送る上で周りと差が出る、又は、その子自身に不利益が出ると考えられる子どもの割合が示されたわけです。
さて、だからと言って治療をして治す、というものではありません。周りにいる人たちがその人の特性を理解し行動さえすればいいのです。(もちろん本人の自覚も必要ですが…)
大人になってもそういった特性は消えるのもではないので、
学校だけではなく、大人社会でも何かの参考になれば幸いです。
ヒント①:具体的な時間を示す
→落ち着きがなくなってきた人がいるとします。「もう少しだから我慢して。」ではなく、「あと10分で終わるから、それまで我慢して。」と伝えると、見通しがつきやすく、途切れがちな集中力がもつことがあるそうです。自分が考える”もう少し”と相手が考える”もう少し”は同じでない場合があります。
ヒント②:具体的な「もの」を示す
→ある物を移動してほしいとき。「これ、あっちに持ってって。」では伝わりにくいようです。そんなときは「この箱、隣の部屋に持ってって。」と言いましょう。指し言葉(これ・それ・あれなど)が何を示しているのか想像するのが苦手な特性があるので、抽象的な表現は避け、具体的な表現に変えるとよいようです。
ヒント③:環境を変える
→『もうそろそろ帰ってほしいのに、全くこちらの気持ちを察せてないなぁ。』と思うときはありませんか?相手の気持ちを推し量る、ということが苦手な人もいますので、そんなときは窓のカーテンを閉めたりして帰る準備を始めるなどの環境を変えると、『あ、帰る時間なんだな。』と相手も理解できるようです。
以上、色々と書きましたが、個性が一人一人違うように、同じ”困った”に対しても、対応は一人一人違うのが一般的なようです。上記のことは、私の経験から得たことも多いので、みなさんの中で応用していただければと思います。
長々と、おつきあいありがとうございました。対応についてはこれからも試行錯誤で頑張りたいと思います。
amazonお買い物はこちらより